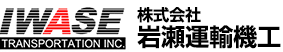月別アーカイブ: 2025年4月
春の交通安全と「ゾーン30」:住宅街での安全運転を改めて見直そう

はじめに:春の訪れとともに増える交通リスク
春は新しい生活が始まる季節です。新入学や新入園を迎えた子どもたちが、これまでとは異なる時間帯・経路で通学し始め、通学路を歩く人の顔ぶれも変化します。特に住宅街では、小さな子どもたちや自転車、歩行者が不意に飛び出してくることがあり、運転者にとって注意すべき点が増える時期です。
そんな中、住宅街の安全性向上のために導入されているのが「ゾーン30」と「ゾーン30プラス」。今回は、この2つの交通安全対策について、改めてその目的や仕組みを確認し、私たち運転者ができることを見直していきましょう。
ゾーン30とは?:生活道路の交通安全対策
「ゾーン30」は、警察庁と国土交通省が連携して推進している取り組みで、主に住宅街や学校周辺などの「生活道路」に設けられた区域を指します。この区域内では、自動車の最高速度が「時速30キロ」に制限されています。
なぜ30キロなのか?
時速30kmで走行していれば、万が一の接触時の被害を大幅に軽減できることが分かっています。特に歩行者や自転車との接触事故の場合、速度が10キロ違うだけでも生死を分けることがあります。ゾーン30は、子どもや高齢者が多く通行する地域の「命を守る減速帯」なのです。
ゾーン30の特徴
「ゾーン30」は単なる速度制限だけではありません。以下のような総合的な安全対策が講じられています。
- 速度規制(30km/h):区域全体にわたっての一律速度制限。
- 区域表示:入口に「ゾーン30」の標識が設置され、ドライバーに明確に伝えられます。
- 物理的対策:ハンプ(道路の隆起)や狭さく(道路を意図的に狭くする)などにより、スピードを自然に落とす構造が導入されています。
- 歩行者優先の空間設計:横断歩道や見通しのよい交差点の設計が進められています。
こうした対策の結果、ゾーン30導入地域では、交通事故件数が実際に減少していることが報告されています。
「ゾーン30プラス」とは?:さらなる安全強化を目指す取り組み
最近では、「ゾーン30」より一歩進んだ「ゾーン30プラス」の導入も進められています。「プラス」とは何か?というと、それは「交通安全のハードルをもう一段階引き上げた区域」ということです。
ゾーン30プラスの具体的な施策
「ゾーン30プラス」は、30km/h制限に加えて、以下のような追加対策が実施されます。
・一方通行の導入
・道路の色分け(視覚的なゾーン化)
・デジタルサイネージによる速度注意喚起
・スクールゾーンとの連携強化
・地域住民と連携した見守り活動
単なる速度制限だけではなく、地域全体で交通安全に取り組む「ソーシャルセーフティネット」の一環として位置づけられているのが、このゾーン30プラスです。
トラックドライバーに求められる意識と配慮
岩瀬運輸機工のような精密機械輸送・重量物輸送を担うプロフェッショナルな運転手にとって、「ゾーン30」はただの規制ではありません。「大きく重い車両が住宅街に入る」というだけで、周囲の緊張感は一気に高まります。
注意すべきポイント
早めの減速と徐行
ゾーンに入る前から減速を開始し、静かなエンジン音での進入を心がけましょう。
視界の確保とミラー確認の徹底
子どもの飛び出しを想定し、交差点や曲がり角では停止を前提とした運転を。
バックや切り返し時の誘導者配置
大型車の死角は予想以上に広く、サイドミラーだけでは見えない部分も多く存在します。必要に応じて後方確認のサポートを行いましょう。
デジタコやドラレコによる記録
日常的な記録が「見える化」に繋がり、運転習慣の改善にも有効です。
地域と共に交通安全を育む
ゾーン30やゾーン30プラスは、単なる「規制」ではなく、地域の安心・安全を守るための「共通言語」です。地域の通学路や生活道路を日常的に通行する私たちドライバーにとって、その意義を理解し、実践することは重要な社会的責任でもあります。
「見えない信号」に気づく心構えを
子どもたちの小さな一歩、通園バスから降りる瞬間、郵便配達員の自転車――それらはすべて、「止まって、注意して、譲るべき合図」かもしれません。交通安全は、法令の遵守だけではなく、他者への思いやりから始まります。
まとめ
春は命が動き出す季節。新しい生活に胸をふくらませる子どもたちや、その家族を見守る地域の目に応えるためにも、私たち運送業界のプロドライバーがまず先頭を切って安全運転を心がける必要があります。
「ゾーン30」は、命を守る30キロの約束。「ゾーン30プラス」は、地域が育む安全のかたち。
そしてもう一つ、重量物輸送を行う際は、こうしたゾーン30の設定区域をできるだけ避けるルート選定も大切な配慮です。車両が大きくなるほど通行時のリスクは増すため、事前のルート調査や住民への影響の最小化も含め、安全と安心を両立した運行計画が求められます。
春の交通安全運動と合わせて、もう一度、自分の運転を見直す機会を持ってみましょう。
↓↓ 岩瀬運輸機工について詳しくはこちら ↓↓
参考
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/doro/zone30/about_zone30.html
【新年度の安全運転講習】初心に戻る“プロの心得”とは?

はじめに
春は新年度の始まり。新たな仲間の加入や体制変更など、運送業界でもフレッシュな風が吹く季節です。
このタイミングで多くの企業が実施するのが「安全運転講習」。
とくにプロドライバーにとっては、“慣れ”が思わぬ事故を招くこともあり、この時期に改めて初心に立ち返ることが大切です。
今回は、新年度におすすめしたい安全運転講習のポイントや、プロドライバーとしての「心得」についてご紹介します。
なぜ新年度に安全運転講習を行うのか
新年度は多忙な時期であると同時に、環境の変化が多く、ドライバーにとって注意力が散漫になりやすい時期です。
特に以下のような要素が重なるため、安全運転への意識を再確認する意義があります:
– 新人ドライバーの入社・育成
– 配送ルートの変更
– 季節の変わり目(春特有の強風や花粉、雨天)
– 周囲の交通状況(新生活に慣れていない一般ドライバーや自転車通学者の増加)
また、近年では高齢ドライバーの増加や多様化する車両・運行形態など、状況は複雑さを増しています。
だからこそ、新年度のタイミングで“心を整える”ことが、事故防止の第一歩となります。
プロドライバーの“初心”とは何か?
新年度の講習で改めて確認しておきたい、プロドライバーの基本行動と心得を以下にまとめます。
【1】「止まる・見る・譲る」の徹底
安全確認の基本。交差点、見通しの悪い場所ではとにかく“止まる”意識を。
相手に譲ることで、自分と荷物を守るのがプロの判断です。
【2】車間距離は「守る」より「余裕を持つ」
荷の重さ、車両のブレーキ性能、天候などにより必要な車間距離は変化します。
安全は「計算」ではなく「余裕」が守ります。
【3】日常点検は「命を預かる整備」
ブレーキ、タイヤ、灯火類、バックカメラなど、毎日チェックする習慣を。
「今日はいいや」が大事故につながることもあります。
【4】“見えないリスク”を想定する
歩行者の急な飛び出し、右直事故、死角の二輪車…日常的に潜むリスクを常にシミュレーションしておく。
【5】無理なスケジュール・指示にノーと言える勇気
「間に合わない」からと無理な追越しや速度超過をするのではなく、まずは会社と相談を。
多くの運送会社で実施されている「安全文化の育成」
新年度のスタートに合わせて、安全運転への意識づけに注力する運送会社も多くあります。
▶︎ 年間安全目標の共有
ドライバー全員で「今年の安全目標」を掲げ、共通意識を持つ企業が増えています。
例:「重大事故ゼロ」「ヒヤリ・ハット報告月10件」など、具体的で現実的な指標。
▶︎ 安全運転講習の実施
実技と座学を組み合わせ、Gロガーによる走行解析やドラレコ映像の振り返りを行うケースもあります。
ベテランドライバーによる事故未然防止の体験談を共有するなど、実践的な講習が重視されています。
▶︎ 新人教育の充実
同乗指導や走行後のフィードバックにより、安全意識と運転技術を習得。
扱う車両や設備に応じた専門的な教育も行われます。
▶︎ “ありがとう”が飛び交う現場づくり
お互いの運転に感謝や声掛けをする文化を育てることで、職場の雰囲気が良くなり、
結果的に事故の防止にもつながります。
新生活者に向けた“注意喚起”も忘れずに
春は、新しい環境に慣れていない一般車・自転車・歩行者が増加します。
プロドライバーは以下の点にも注意が必要です:
– 自転車通学者の予測不能な動き(特に雨天や登下校時間帯)
– 初心者マークの自動車との接触リスク
– 横断歩道での歩行者優先(交通ルール改正の影響も)
事故の加害者・被害者を問わず、トラックが関与するだけで影響は大きくなります。
だからこそ、プロとしての“ゆとり”と“心の広さ”が試される季節です。
デジタル活用で「見える安全」へ
近年、AIドラレコや運行管理システムを活用した「見える化」が進んでいます。
多くの運送会社では以下のような取り組みが実施されています:
– ドライバーごとのGロガーデータを分析し、急加減速やカーブでの挙動を改善
– ドラレコ映像でヒヤリ場面を共有し、全員の教材とする
– 安全運転表彰制度を導入し、モチベーションアップにも寄与
テクノロジーは万能ではありませんが、「気づき」を促すツールとして非常に有効です。
まとめ:原点に戻ることが、最先端の安全対策
安全運転において、「初心」は決して過去に戻ることではなく、進化のスタートラインです。
どれだけ経験を重ねても、どれだけ技術が進んでも、「基本を守る」「心を整える」ことの価値は変わりません。
新年度の安全運転講習は、そんな“プロとしての原点”に立ち返る大切な機会。
多くの運送現場で、安全第一の輸送が引き続き追求されることを願ってやみません。
↓↓ 岩瀬運輸機工について詳しくはこちら ↓↓
出典:
国土交通省|トラック運送業の安全対策
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000002.html
全日本トラック協会|安全・環境への取り組み
運行管理業務と安全マニュアル
2025年春の全国交通安全運動 〜新たな取り組みと企業・ドライバーが意識すべき安全ポイント〜

はじめに
毎年恒例となっている「春の全国交通安全運動」が、2025年も4月6日(日)から15日(土)までの10日間にわたって全国で実施されます。これは交通事故防止を目的とした国民運動であり、警察庁および都道府県警察、自治体、関係団体が一体となって取り組むキャンペーンです。
特に今年は、改正された道路交通法の施行(2024年11月)や「自転車のルール違反に対する取り締まり強化」が重なり、例年以上に注目すべきポイントが多く存在します。本記事では、2025年春の交通安全運動の概要と、輸送業界を含むドライバー全体に関係するトピックを中心に解説していきます。
運動の基本方針と重点目標(2025年)
警察庁が発表した今年の交通安全運動の基本方針は次の通りです:
「こどもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保と正しい横断方法の実践」
「歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶やシートベルト・チャイルドシートの適切な使用の促進」
「自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底」
このうち、特に注目されているのが【自転車の安全利用】と【横断歩道の安全確保】です。これは2024年に施行された道路交通法の改正によって、自転車運転に対する罰則が強化されたことが背景にあります。
自転車利用者への取り締まりが強化
2024年11月の法改正により、「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に関する罰則が強化され、自転車運転にも“青切符”制度(軽微な違反に対する反則金)が導入されました。
これにより、以下のような違反行為に対しても摘発されやすくなります:
・飲酒運転
・片手運転(傘さし等)
・イヤホン使用
・無灯火走行
・一時停止無視
・二人乗り
・並進の禁止
特に通学時間帯や夕方の帰宅ラッシュ時には、トラックや業務車両と自転車が交差する場面も多く、運送業のドライバーにとっても事故リスクの増大につながります。したがって、周囲の自転車の動きにいっそう注意を払う必要があります。
横断歩道の「歩行者優先」の徹底
警視庁の調査によると、横断歩道での歩行者妨害は依然として多く、全国的にも大きな課題となっています。2025年の春の交通安全運動では、特に「横断歩道における一時停止の徹底」が求められており、トラックやバスなど大型車両の停止義務違反に対しても、取締が強化される見込みです。
特に薄暮時(夕方16〜18時)や夜間帯は、歩行者が見えづらくなる時間帯であり、ドライバーは早めのヘッドライト点灯と、交差点手前でのスピードダウンを徹底しましょう。
安全運転を支える企業としての取組み
岩瀬運輸機工では、これまでから安全運転教育を通じて「衝撃の見える化」を進めてきました。精密機械輸送を専門とする当社にとって、安全なドライビング技術は企業価値そのものです。
また、運転者にとっては見落としがちな「ながら運転」や、「脇見運転」などのヒューマンエラーも、繁忙期には発生しやすくなります。企業としても日常的な運転環境の改善と心理的負担の軽減が必要不可欠です。
交通安全は社会全体の取り組み
物流業界にとって、交通安全は一企業の問題ではありません。トラックは日本の生活インフラを支える存在であり、私たちの安全運転が地域社会や他の交通参加者の命を守ることにつながります。
また、春は新入学・新社会人の季節でもあり、交通ルールに不慣れな歩行者や自転車利用者が増える時期です。ドライバーは、初心者の動きを予測する意識を持ち、「止まる」「譲る」「確認する」を徹底しましょう。
最後に:春の交通安全運動にどう向き合うか
今年の春の交通安全運動は、法改正によって新たな取り組みが講評されています。
・自転車の取締強化によるリスク意識の向上
・横断歩道でのマナー向上と一時停止の徹底
・大型車・業務車両の責任ある走行
これらはすべて、事故ゼロ社会の実現に向けた大切なステップです。岩瀬運輸機工では、今年もドライバー一人ひとりがこの運動の意義を深く理解し、プロとしての安全意識を高める機会ととらえています。
↓↓ 岩瀬運輸機工について詳しくはこちら ↓↓
参考
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/safety_campaign.html
2025年入社式

4月1日、弊社では本社にて入社式を執り行いました。
今年は、IWASEグループで新たに6名の新入社員を迎えることができました。
入社式では、社長から一人ひとりに入社辞令が手渡され、新入社員の皆さんの緊張した面持ちの中にも、
これからの挑戦への期待が感じられました。
その後、新入社員それぞれが自己紹介とともに抱負を語り、一言ひとことに社会人としての決意と意気込みが込められていました。


社内には新たな仲間を迎えた喜びと期待が広がり、入社式を通じて新入社員と既存メンバーのつながりがより深まりました。これから共に学び、成長しながら、新たな挑戦に向かって歩んでいけることを楽しみにしています。