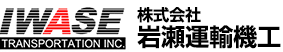seisaku2 のすべての投稿
【新年度の安全運転講習】初心に戻る“プロの心得”とは?

はじめに
春は新年度の始まり。新たな仲間の加入や体制変更など、運送業界でもフレッシュな風が吹く季節です。
このタイミングで多くの企業が実施するのが「安全運転講習」。
とくにプロドライバーにとっては、“慣れ”が思わぬ事故を招くこともあり、この時期に改めて初心に立ち返ることが大切です。
今回は、新年度におすすめしたい安全運転講習のポイントや、プロドライバーとしての「心得」についてご紹介します。
なぜ新年度に安全運転講習を行うのか
新年度は多忙な時期であると同時に、環境の変化が多く、ドライバーにとって注意力が散漫になりやすい時期です。
特に以下のような要素が重なるため、安全運転への意識を再確認する意義があります:
– 新人ドライバーの入社・育成
– 配送ルートの変更
– 季節の変わり目(春特有の強風や花粉、雨天)
– 周囲の交通状況(新生活に慣れていない一般ドライバーや自転車通学者の増加)
また、近年では高齢ドライバーの増加や多様化する車両・運行形態など、状況は複雑さを増しています。
だからこそ、新年度のタイミングで“心を整える”ことが、事故防止の第一歩となります。
プロドライバーの“初心”とは何か?
新年度の講習で改めて確認しておきたい、プロドライバーの基本行動と心得を以下にまとめます。
【1】「止まる・見る・譲る」の徹底
安全確認の基本。交差点、見通しの悪い場所ではとにかく“止まる”意識を。
相手に譲ることで、自分と荷物を守るのがプロの判断です。
【2】車間距離は「守る」より「余裕を持つ」
荷の重さ、車両のブレーキ性能、天候などにより必要な車間距離は変化します。
安全は「計算」ではなく「余裕」が守ります。
【3】日常点検は「命を預かる整備」
ブレーキ、タイヤ、灯火類、バックカメラなど、毎日チェックする習慣を。
「今日はいいや」が大事故につながることもあります。
【4】“見えないリスク”を想定する
歩行者の急な飛び出し、右直事故、死角の二輪車…日常的に潜むリスクを常にシミュレーションしておく。
【5】無理なスケジュール・指示にノーと言える勇気
「間に合わない」からと無理な追越しや速度超過をするのではなく、まずは会社と相談を。
多くの運送会社で実施されている「安全文化の育成」
新年度のスタートに合わせて、安全運転への意識づけに注力する運送会社も多くあります。
▶︎ 年間安全目標の共有
ドライバー全員で「今年の安全目標」を掲げ、共通意識を持つ企業が増えています。
例:「重大事故ゼロ」「ヒヤリ・ハット報告月10件」など、具体的で現実的な指標。
▶︎ 安全運転講習の実施
実技と座学を組み合わせ、Gロガーによる走行解析やドラレコ映像の振り返りを行うケースもあります。
ベテランドライバーによる事故未然防止の体験談を共有するなど、実践的な講習が重視されています。
▶︎ 新人教育の充実
同乗指導や走行後のフィードバックにより、安全意識と運転技術を習得。
扱う車両や設備に応じた専門的な教育も行われます。
▶︎ “ありがとう”が飛び交う現場づくり
お互いの運転に感謝や声掛けをする文化を育てることで、職場の雰囲気が良くなり、
結果的に事故の防止にもつながります。
新生活者に向けた“注意喚起”も忘れずに
春は、新しい環境に慣れていない一般車・自転車・歩行者が増加します。
プロドライバーは以下の点にも注意が必要です:
– 自転車通学者の予測不能な動き(特に雨天や登下校時間帯)
– 初心者マークの自動車との接触リスク
– 横断歩道での歩行者優先(交通ルール改正の影響も)
事故の加害者・被害者を問わず、トラックが関与するだけで影響は大きくなります。
だからこそ、プロとしての“ゆとり”と“心の広さ”が試される季節です。
デジタル活用で「見える安全」へ
近年、AIドラレコや運行管理システムを活用した「見える化」が進んでいます。
多くの運送会社では以下のような取り組みが実施されています:
– ドライバーごとのGロガーデータを分析し、急加減速やカーブでの挙動を改善
– ドラレコ映像でヒヤリ場面を共有し、全員の教材とする
– 安全運転表彰制度を導入し、モチベーションアップにも寄与
テクノロジーは万能ではありませんが、「気づき」を促すツールとして非常に有効です。
まとめ:原点に戻ることが、最先端の安全対策
安全運転において、「初心」は決して過去に戻ることではなく、進化のスタートラインです。
どれだけ経験を重ねても、どれだけ技術が進んでも、「基本を守る」「心を整える」ことの価値は変わりません。
新年度の安全運転講習は、そんな“プロとしての原点”に立ち返る大切な機会。
多くの運送現場で、安全第一の輸送が引き続き追求されることを願ってやみません。
↓↓ 岩瀬運輸機工について詳しくはこちら ↓↓
出典:
国土交通省|トラック運送業の安全対策
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000002.html
全日本トラック協会|安全・環境への取り組み
運行管理業務と安全マニュアル
2025年春の全国交通安全運動 〜新たな取り組みと企業・ドライバーが意識すべき安全ポイント〜

はじめに
毎年恒例となっている「春の全国交通安全運動」が、2025年も4月6日(日)から15日(土)までの10日間にわたって全国で実施されます。これは交通事故防止を目的とした国民運動であり、警察庁および都道府県警察、自治体、関係団体が一体となって取り組むキャンペーンです。
特に今年は、改正された道路交通法の施行(2024年11月)や「自転車のルール違反に対する取り締まり強化」が重なり、例年以上に注目すべきポイントが多く存在します。本記事では、2025年春の交通安全運動の概要と、輸送業界を含むドライバー全体に関係するトピックを中心に解説していきます。
運動の基本方針と重点目標(2025年)
警察庁が発表した今年の交通安全運動の基本方針は次の通りです:
「こどもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保と正しい横断方法の実践」
「歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶やシートベルト・チャイルドシートの適切な使用の促進」
「自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底」
このうち、特に注目されているのが【自転車の安全利用】と【横断歩道の安全確保】です。これは2024年に施行された道路交通法の改正によって、自転車運転に対する罰則が強化されたことが背景にあります。
自転車利用者への取り締まりが強化
2024年11月の法改正により、「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に関する罰則が強化され、自転車運転にも“青切符”制度(軽微な違反に対する反則金)が導入されました。
これにより、以下のような違反行為に対しても摘発されやすくなります:
・飲酒運転
・片手運転(傘さし等)
・イヤホン使用
・無灯火走行
・一時停止無視
・二人乗り
・並進の禁止
特に通学時間帯や夕方の帰宅ラッシュ時には、トラックや業務車両と自転車が交差する場面も多く、運送業のドライバーにとっても事故リスクの増大につながります。したがって、周囲の自転車の動きにいっそう注意を払う必要があります。
横断歩道の「歩行者優先」の徹底
警視庁の調査によると、横断歩道での歩行者妨害は依然として多く、全国的にも大きな課題となっています。2025年の春の交通安全運動では、特に「横断歩道における一時停止の徹底」が求められており、トラックやバスなど大型車両の停止義務違反に対しても、取締が強化される見込みです。
特に薄暮時(夕方16〜18時)や夜間帯は、歩行者が見えづらくなる時間帯であり、ドライバーは早めのヘッドライト点灯と、交差点手前でのスピードダウンを徹底しましょう。
安全運転を支える企業としての取組み
岩瀬運輸機工では、これまでから安全運転教育を通じて「衝撃の見える化」を進めてきました。精密機械輸送を専門とする当社にとって、安全なドライビング技術は企業価値そのものです。
また、運転者にとっては見落としがちな「ながら運転」や、「脇見運転」などのヒューマンエラーも、繁忙期には発生しやすくなります。企業としても日常的な運転環境の改善と心理的負担の軽減が必要不可欠です。
交通安全は社会全体の取り組み
物流業界にとって、交通安全は一企業の問題ではありません。トラックは日本の生活インフラを支える存在であり、私たちの安全運転が地域社会や他の交通参加者の命を守ることにつながります。
また、春は新入学・新社会人の季節でもあり、交通ルールに不慣れな歩行者や自転車利用者が増える時期です。ドライバーは、初心者の動きを予測する意識を持ち、「止まる」「譲る」「確認する」を徹底しましょう。
最後に:春の交通安全運動にどう向き合うか
今年の春の交通安全運動は、法改正によって新たな取り組みが講評されています。
・自転車の取締強化によるリスク意識の向上
・横断歩道でのマナー向上と一時停止の徹底
・大型車・業務車両の責任ある走行
これらはすべて、事故ゼロ社会の実現に向けた大切なステップです。岩瀬運輸機工では、今年もドライバー一人ひとりがこの運動の意義を深く理解し、プロとしての安全意識を高める機会ととらえています。
↓↓ 岩瀬運輸機工について詳しくはこちら ↓↓
参考
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/safety_campaign.html
2025年入社式

4月1日、弊社では本社にて入社式を執り行いました。
今年は、IWASEグループで新たに6名の新入社員を迎えることができました。
入社式では、社長から一人ひとりに入社辞令が手渡され、新入社員の皆さんの緊張した面持ちの中にも、
これからの挑戦への期待が感じられました。
その後、新入社員それぞれが自己紹介とともに抱負を語り、一言ひとことに社会人としての決意と意気込みが込められていました。


社内には新たな仲間を迎えた喜びと期待が広がり、入社式を通じて新入社員と既存メンバーのつながりがより深まりました。これから共に学び、成長しながら、新たな挑戦に向かって歩んでいけることを楽しみにしています。
岩瀬運輸機工の主力「低床式幅広総輪エアサスペンショントレーラー」

目次
はじめに
岩瀬運輸機工では、総輪エアサス、後輪ステアリング付の低床式幅広総輪エアサスペンショントレーラーを使用した精密機械の輸送サービスを提供しています。
このトレーラーは、背の高い荷物や重量のある精密機械を安全かつ確実に輸送するための特別な設計が施されています。
今回は、この低床式幅広トレーラーの特長や利点についてご紹介します。
精密機械の輸送に低床式幅広トレーラーを使用する理由
精密機械は、内部の構造が非常に繊細であるため、輸送時の振動や衝撃によって故障のリスクがあります。また、これらの機械は重量があるだけでなく、背の高いものや幅広いものも多いため、通常のトレーラーでは対応が難しい場合があります。岩瀬運輸機工では、こうした課題に対応するため、低床式幅広総輪エアサスペンショントレーラーを採用しています。
荷台が低いメリット
■ 高さ制限をクリア
荷台が低いため、トンネルや陸橋の高さ制限があるルートでも柔軟に対応可能です。輸送ルートの選択肢が広がり、納期を守ることができます。
■ 重心が安定する
荷物を低い位置に積載できるため、車両全体の重心が低くなり、カーブや傾斜での安定性が向上します。これにより、大型精密機械にかかる負荷を低減し損傷リスクを減らせます。
幅広荷台の特長 – 特殊形状の荷物にも対応 –
低床幅広の荷台設計により、通常のトレーラーでは積載が難しい大型機械や特殊形状の荷物も安全に運搬可能です。
また、幅広い荷台は、荷物が左右にずれるリスクを軽減します。輸送中の安定性が確保されるため、安心してお任せいただけます。
エアサスペンションの利点
低床式幅広トレーラーのもう一つの特長は、エアサスペンションを搭載していることです。エアサスペンションは、輸送中の振動や衝撃を最小限に抑える重要な役割を果たします。
振動吸収による荷物保護
精密機械は、微小な振動でも性能に影響を与えることがあります。エアサスペンションは、路面の凹凸から生じる振動を吸収し、荷台に伝わる衝撃を軽減します。
この高度な振動吸収性能により、内部部品のズレや損傷を防ぎます。また、路面が荒れている場合でも、エアサスペンションが衝撃を吸収するため、機械が安全に目的地まで届きます。
高い安定性
エアサスペンションは、積載荷物の重量に応じて車体を自動調整する機能を持っています。これにより、常に車両が水平を保ち、安定した輸送を実現します。
後輪ステアリングのメリット
後輪ステアリングとは、トレーラーの後輪が旋回方向に応じて自動的に動くシステムです。この機能により、以下のようなメリットがあります
狭い道路でもスムーズに走行可能
一般的なトレーラーでは曲がりきれない狭い道路や交差点も、後輪ステアリングにより後輪が旋回方向に追従するため、余裕を持って通過できます。都市部や工場敷地内のようなスペースが限られた環境で特に有効です。
駐車や積み下ろしが容易
狭いスペースでも車両を正確に駐車できるため、積み下ろし作業の効率が向上します。特に、荷降ろし時の安全性が高まる点は、お客様にとって大きな安心材料です。
岩瀬運輸機工のサービスの強み
タイヤは、トラックの走行性能や安全性を左右する重要な部品です。主な役割は以下の通りです。
お客様のニーズに合わせた柔軟な対応
岩瀬運輸機工では、お客様が求める輸送条件に合わせたプランを提案します。
•高さや幅の制約がある荷物の輸送
•振動を極力抑える必要がある精密機械の運搬
•納期厳守の輸送スケジュール対応
安全第一の輸送体制
当社のドライバーは、豊富な経験と技術を持つ輸送のプロフェッショナルです。低床式幅広総輪エアサスペンショントレーラーの特性を熟知しており、荷物の安全性を第一に考えた運転を行います。
■ 高品質な車両メンテナンス
輸送車両は定期的にメンテナンスを実施し、常に最高の状態を保っています。これにより、輸送中のトラブルを防ぎ、お客様の荷物を確実にお届けします。
■ 岩瀬運輸機工の精密機械輸送サービスを選ぶ理由
•輸送のプロがサポート
豊富な知識と経験を持つスタッフが、お客様の荷物に最適な輸送計画を立てます。
•高性能トレーラーをはじめとした専用輸送車両を完備
振動吸収や安定性に優れた車両で、安全・確実な輸送を実現します。
•きめ細やかな対応
お客様のニーズに応じた柔軟なサービス提供が可能です。
まとめ
岩瀬運輸機工が提供する低床式幅広総輪エアサスペンショントレーラーを使用した輸送サービスは、大型精密機械の輸送に最適です。高い振動吸収性能や安定性を活かし、お客様の大切な荷物を安全に目的地までお届けします。
精密機械輸送に関するご相談やご依頼は、ぜひ岩瀬運輸機工までお問い合わせください。お客様のニーズに寄り添い、最適な輸送プランをご提案いたします。
岩瀬運輸機工について詳しくは《こちら》から

重い荷物をけん引する トレーラーヘッド:エンジン性能、安全技術、エコへの挑戦

トレーラーヘッドとは?
トレーラーヘッドは、物流業界において大型貨物の輸送を支える重要な存在です。その性能や技術は日々進化しており、安全性や環境性能の向上が求められています。
トレーラーヘッドとは、トレーラー(荷台部分)をけん引するための車両を指します。「トラクターヘッド」「トラクター」とも呼ばれ、物流の業界用語では「アタマ」とも呼ばれることがあります。荷台部分と分離した構造が特徴で、貨物を載せるトレーラーを連結してけん引する役割を持ち、大型貨物や長距離輸送に特化した設計となっています。トレーラーヘッドには高いけん引力や安定性が求められるため、一般的なトラックとは異なる構造や性能を持っています。
トレーラーヘッドの基本構造とエンジン性能
トレーラーヘッドは、トレーラー(荷台部分)をけん引する役割を持つ車両です。重い貨物を運ぶため、高出力かつ高いトルク性能が求められます。現在主流となっているのはディーゼルエンジンを搭載したモデルですが、燃費性能を向上させるためのさまざまな技術が進化しています。
高出力エンジンと燃費性能の向上
トレーラーヘッドには、重い貨物をけん引するために大排気量エンジンが搭載されていますが、近年では排気ガス規制への対応や燃費向上のため、高圧燃料噴射システムやターボチャージャー技術が採用されています。また、エネルギー効率を最大化するための低摩擦部品やエンジン制御システムも進化しています。
さらに、燃費向上のために多段オートマチックトランスミッション(多段AT)を採用する動きが広がっています。多段ATは、エンジン回転数を効率的に調整し、無駄な燃料消費を抑えると同時に滑らかな運転を実現します。これにより、長距離輸送時の燃費効率が大幅に改善され、環境負荷の軽減にもつながっています。
電動化の可能性
電動化の波はトレーラーヘッドにも及んでおり、一部のメーカーが電動モデルを試験的に投入しています。ただし、大型車両特有の長距離輸送や高負荷運転において、現行のバッテリー技術では実用化が難しいという課題があります。
最新の安全装備と技術革新
トレーラーヘッドはその巨大な車体ゆえに、安全性能が特に重要視されます。近年のモデルには最先端の安全技術が導入され、事故リスクの低減に貢献しています。ただし、一般車両よりも寿命が長いトレーラーヘッドは、最新の安全装備が備わっていない車両も依然として多く走行している現状があります。このため、車両管理においても安全性の確保が重要な課題となっています。
自動運転支援技術
長距離を安全に運転するため、ドライバーの快適装備も工夫されています。例えば、仮眠のためのベッドが備わっている車両も多く、長時間の運行でもドライバーが適切に休息を取れるよう配慮されています。
現在、多くのトレーラーヘッドには自動運転支援システムが搭載されています。代表的な技術としては、アダプティブクルーズコントロール(ACC)、車線維持支援システム(LKA)、衝突被害軽減ブレーキ(AEBS)が挙げられます。これらの機能により、長距離運転時のドライバーの負担が軽減され、事故のリスクを最小化します。
夜間や悪天候時の安全性向上
LEDライトや赤外線カメラを用いた視界補助システムが普及しつつあります。これにより、夜間や悪天候時の安全性が向上し、ドライバーが安心して運転できる環境が整備されています。
環境性能とエコへの取り組み
環境問題への意識が高まる中、トレーラーヘッドにもエコ性能が求められています。特に燃費向上と排出ガス削減の取り組みが加速しています。
運転席空調の独立システム
トレーラーヘッドは長時間にわたる待機時間が発生する用途が多く、この間もドライバーの快適性を維持する必要があります。そのため、エンジンとは独立したキャビンエアコンが設けられているモデルが普及しています。このシステムにより、エンジンを停止した状態でも運転席の空調が作動し、燃料消費と排出ガスを削減することが可能です。
電動トレーラーヘッドの現状と課題
環境問題への意識が高まる中、トレーラーヘッドにもエコ性能が求められています。特に燃費向上と排出ガス削減の取り組みが加速しています。
電動トレーラーヘッドの現実性は?
電動トレーラーヘッドは、環境負荷を大幅に削減できる可能性を秘めていますが、現状では課題が多いです。大型車両の高エネルギー需要に対して、現在のバッテリー技術では航続距離や充電時間の面で不十分です。また、高速道路や物流拠点における充電インフラの整備も進んでいません。
ハイブリッドモデルの現実性
フル電動化が進むまでの過渡期として、ディーゼルエンジンと電動モーターを組み合わせたハイブリッドモデルが注目されています。この技術により、燃費を向上させつつ排出ガスを削減する現実的なソリューションが提供されています。
規制とメーカーの対応
日本では、ポスト新長期規制と呼ばれる厳しい排出ガス規制が導入されています。いすゞや三菱ふそうはこれに対応するモデルを投入し、環境性能を高める努力を続けています。
トレーラーヘッドの未来
トレーラーヘッドの未来は、技術革新と規制の進展により大きく変わろうとしています。
自動運転と完全電動化の展望
完全自動運転トラックの開発が進む中、トレーラーヘッドの運行効率はさらに向上すると予想されます。また、水素燃料電池など新しいエネルギー源の導入も期待されています。ただし、これらの技術が商業レベルで実用化されるには、まだ時間が必要です。
サステナブルな物流への貢献
トレーラーヘッドの進化は、輸送効率の向上だけでなく、環境負荷の軽減にも貢献します。メーカーと物流企業が連携し、持続可能な物流を実現することが求められています。
まとめ
トレーラーヘッドの技術革新は、安全性や環境性能の向上に貢献し、物流業界全体を支えています。一方で、電動化や完全自動運転の実現にはまだ課題が多く、これらを克服することで、さらなる進化が期待されます。
岩瀬運輸機工としても、こうした最新技術を取り入れながら、高品質で環境に配慮した輸送サービスを提供し続けてまいります。
岩瀬運輸機工について詳しくはこちら ↓↓
トラックのディーゼルエンジンの環境負荷低減技術

はじめに
トラック輸送は、日本の物流の大部分を担っており、その動力源としてディーゼルエンジンが主流となっています。しかし、ディーゼルエンジンは窒素酸化物(NOx)や粒子状物質(PM)を排出するため、環境負荷の低減が求められています。
特に、日本の「ポスト新長期規制(平成28年規制)」や欧州の「Euro 6」など、排出ガス規制が強化される中、ディーゼルエンジンのクリーン化が急務となっています。本記事では、ディーゼルエンジンの環境負荷を低減する最新技術や代替燃料の活用について詳しく解説します。
ディーゼルエンジンの環境規制の変遷
ディーゼルエンジンの排出ガス規制は、年々厳しくなっています。
例えば、日本の「平成28年規制」では、NOxは0.4g/kWh、PMは0.01g/kWh以下とされ、2000年以前の基準と比較すると90%以上の削減が求められています。
このような規制をクリアするため、エンジンメーカーは排ガス後処理技術や燃焼効率の向上に取り組んでおり、クリーンディーゼル技術が進化しています。
ディーゼルエンジンの環境負荷低減技術
ディーゼル微粒子除去装置(DPF: Diesel Particulate Filter)
DPFは、排気ガス中のPM(粒子状物質)を捕集し、燃焼させて除去するシステムです。
この技術により、排出されるPMを大幅に低減できますが、フィルターの目詰まりによる燃費悪化が課題とされてきました。近年では自動再生機能を備えたDPFが登場し、メンテナンス負担の軽減が図られています。
尿素SCRシステム(Selective Catalytic Reduction)
SCRは、尿素水(AdBlue)を排気ガス中に噴射し、NOxを無害な窒素と水に分解する技術です。
このシステムを活用することで、NOxの排出量を大幅に削減できるため、現在のディーゼルエンジンには必須の技術となっています。ただし、AdBlueの補充が必要であり、寒冷地では凍結のリスクがあるため加温装置が搭載されています。
高効率燃焼技術
エンジンの燃焼効率を高めることで、燃料の無駄を削減し、CO2やNOxの排出を抑えることができます。
特に、以下の技術が活用されています。
高圧縮比エンジン:燃焼効率を向上させ、燃料消費量を削減
可変ジオメトリーターボ(VGT):エンジン回転数に応じた最適な過給圧を提供し、燃焼効率を改善
クリーンディーゼル技術:燃料噴射の最適化により、PMやNOxの発生を抑制
代替燃料の活用
▶︎ バイオディーゼル燃料(BDF: Biodiesel Fuel)バイオディーゼル燃料は、植物油や動物性脂肪を原料とする再生可能エネルギーで、カーボンニュートラルの概念に基づく燃料として注目されています。
現在、多くの国でB5(5%バイオ燃料混合)、B20(20%混合)などのディーゼル燃料が導入されており、化石燃料の消費削減が進められています。
▶︎ HVO(Hydrotreated Vegetable Oil:水素化植物油)HVOは、植物油を水素化処理した燃料で、通常のディーゼル燃料と比べてCO2排出量を大幅に削減できるという特徴があります。
▶︎ 合成燃料(e-fuel)e-fuelは、再生可能エネルギーを活用して水素とCO2から合成される燃料で、カーボンニュートラルな燃料として期待されています。
車両運用の工夫による環境負荷低減
エコドライブの推進
◇急発進・急加速を避ける
◇最適なエンジン回転数で走行する
◇アイドリングストップを徹底する
を徹底することで、より環境負荷の低い運行が可能となります。
ルート最適化
最新の運行管理システム(TMS: Transportation Management System)を活用し、最適な配送ルートを計画することで、無駄な燃料消費を削減できます。
まとめ
ディーゼルエンジンの環境負荷低減は、排ガス処理技術の進化・代替燃料の活用・運行管理の工夫という3つの視点から進められています。
現在のトラック業界では、DPFやSCRを活用したクリーンディーゼル技術が標準装備され、さらにはバイオディーゼルやHVO、e-fuelといった代替燃料の導入が進められています。
今後、物流業界はより持続可能な輸送を目指し、環境負荷の少ない運行方法を取り入れていくことが求められるでしょう。
岩瀬運輸機工も環境負荷に配慮した運搬を心がけて、持続可能な輸送を目指しています。
岩瀬運輸機構について詳しくはこちら↓↓
参考文献
[平成28年排出ガス規制]
https://www.mlit.go.jp/common/001094623.pdf
自動車用高性能・高信頼性 VG ターボ チャージャの開発
https://www.mhi.co.jp/technology/review/pdf/433/433031.pdf
各国・地域におけるバイオ燃料の導入状況
https://www.pecj.or.jp/wp-content/uploads/2024/04/JPECForum_2024_program_010.pdf
バイオ・低炭素合成燃料という選択肢 ―バイオ・低炭素合成燃料がエネルギートランジションに果たす役割―|JOGMEC石油・天然ガス資源情報ウェブサイト
https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1009992/1010151.html
HVO〈Hydrotreated Vegetable Oils〉 – 一般財団法人環境優良車普及機構
https://www.levo.or.jp/research/tyousa/research-tyousa-4/word-h2/
持続可能な物流へ 〜CNGトラックの利点と導入のポイント〜

はじめに
環境問題への関心が高まる中、トラック業界でもクリーンエネルギーの活用が進んでいます。
その中でも、CNG(圧縮天然ガス)トラックは、ディーゼルエンジンと比較してCO2排出量が少なく、排気ガスがクリーンであることから注目されています。
今回は、CNGトラックの特長やメリット、導入時のポイントについて解説します。
LPGタクシーの普及とCNGとの違い
ガスを使った自動車は日本ではタクシーを中心に普及しています。
LPG(Liquefied Petroleum Gas:液化石油ガス)は、プロパンやブタンを主成分とする燃料で、主にタクシーや一部の商用車に利用されています。一方、CNG(圧縮天然ガス)はメタンを主成分とする燃料で、トラックやバスなどの大型車両に適しています。
【LPGとCNGの主な違い】
成分: LPGはプロパン・ブタン、CNGはメタンが主成分。
貯蔵方法: LPGは液体として低圧で貯蔵されますが、CNGは気体のまま高圧で貯蔵されます。
供給インフラ: LPGは全国に供給網が整備されているが、CNGはインフラ整備が途上です。
タクシーがガソリンではなくLPGを使うメリットは以下の3点です。
01. 環境性能の向上
CO2排出量がガソリン車よりも少なく、温暖化対策に貢献します。
さらに、NOxやPM(粒子状物質)の排出が少なく、大気汚染防止に寄与すると考えられます。
02. 燃料コストの削減
LPGはガソリンより価格が安定しており、ランニングコストを抑えられます。
また税制優遇措置が適用されることが多く、経済的なメリットが期待できます。
03. エンジンの耐久性向上
LPGは燃焼時のカーボン堆積が少なく、エンジンの寿命を延ばす効果があるとされています。
そのため、メンテナンスコストの削減にもつながります。
CNGトラックとは?
CNGトラックとは、圧縮天然ガス(Compressed Natural Gas)を燃料とするトラックのことです。
天然ガスを約200~250気圧に圧縮し、燃料タンクに貯蔵することで、ディーゼルやガソリン車と同様に長距離走行が可能になります。
CNGトラックのメリット
▶︎ 環境負荷の低減
CO2排出量がディーゼル車に比べて約20~30%削減します。
NOx(窒素酸化物)やPM(粒子状物質)の排出が大幅に減少し、大気汚染の防止に貢献すると考えられます。
▶︎ 燃料コストの削減
天然ガスは石油に比べて価格が安定しており、燃料費の変動リスクを抑えられます。
一部の自治体ではCNGトラック導入に補助金制度が適用されることもあります。
▶︎ 静粛性の向上
ディーゼルエンジンに比べ、燃焼音や振動が少なく、ドライバーの負担を軽減します。
CNGトラック導入時のポイント
▶︎ 燃料補給インフラの確認
CNGスタンドはまだ全国的に普及途上のため、運行ルート上に補給設備があるか事前に確認が必要となります。
▶︎ 導入コストの検討
CNGトラックの車両価格はディーゼル車よりも高めですが、長期的な燃料コストや補助金を考慮するとメリットが大きいと考えられます。
▶︎ 運用ノウハウの習得
CNGの特性や燃料補給方法について、ドライバーや整備士への教育も必要となります。
まとめ
CNGトラックは、環境負荷の低減や燃料コスト削減といったメリットを持ち、持続可能な物流の実現に向けて有力な選択肢となります。
導入にはインフラやコスト面での課題もありますが、今後の技術革新やインフラ整備の進展により、さらなる普及が期待されます。
岩瀬運輸機工でも、環境に配慮した輸送手段の導入を積極的に検討していきます。
岩瀬運輸機構について詳しくはこちら↓↓
トラックの水素燃料の現状と未来

はじめに
以前の記事でトラックの脱炭素化について解説しましたが、今回はその中でも水素燃料トラックについて掘り下げて解説します。
近年、環境問題への関心の高まりとともに、トラック業界でも脱炭素化が進んでいます。特に水素燃料を活用した大型トラックの開発が国内外で注目されています。本記事では、水素燃料トラックの開発の歴史、現在の状況、そして将来に向けた課題について見ていきましょう。
現在の水素燃料トラックの状況
海外の動向
欧州では、スイスが水素トラックの導入を先導し、2020年には「Hyundai XCIENT Fuel Cell」が運行を開始しました。このトラックは、世界初の量産型燃料電池大型トラックとして、スイスを皮切りに導入されました。
また、ドイツではダイムラー・トラックが「GenH2 Truck」のプロトタイプを2021年に発表し、2024年半ばから顧客向けテストを開始、2030年後半には量産モデルの導入を目指しています。さらに、ダイムラー・トラックはボルボ・グループとの合弁事業「セルセントリック」を設立し、燃料電池システムの量産体制を強化しています。
一方、米国では、Hyundaiが「XCIENT Fuel Cell」トラックを2023年に初めて公開し、北米市場への参入を目指しています。このトラックは、スイス、ドイツ、イスラエル、韓国、ニュージーランドの5カ国で展開され、累計400万マイル以上の商用運転実績を持っています。
日本国内の動向
日本ではトヨタと日野自動車が協力し、「日野プロフィアFCV」の開発を進めています。2022年には、商業運用を想定した試験走行が開始され、2025年の市場投入を目指しています。また、国土交通省や経済産業省が水素ステーションの整備を支援しており、インフラの拡充が進められています。
さらに、大手物流企業が水素燃料トラックの導入を検討しており、環境負荷の低減に向けた取り組みが進行中です。
水素燃料トラックの開発の歴史
水素燃料の研究は1970年代から進められてきましたが、当初はコストや技術的な課題が多く、商業化には至りませんでした。しかし、2000年代に入ると燃料電池技術の進歩とともに、バスや乗用車向けの燃料電池車(FCV)の実用化が進みました。
トラック分野では、2010年代後半から各国の大手メーカーが水素燃料トラックの開発に本格的に着手。特にスイスの「H2 Energy」、ドイツの「ダイムラー」、アメリカの「ニコラ・モーター」、日本の「トヨタ」「日野自動車」などが積極的に参入し、試験運用が進められてきました。
将来に向けた課題
インフラの整備
水素燃料トラックの普及には、全国的な水素ステーションの整備が不可欠です。現在、日本国内の水素ステーションは都市部を中心に限られており、長距離輸送を行うトラックの運行にはまだ課題があります。
コストの削減
水素燃料電池の製造コストや水素供給コストが依然として高いため、ディーゼルトラックと比較すると経済的なハードルが高いのが現状です。水素の大量生産技術の向上や、グリーン水素(再生可能エネルギー由来の水素)の普及が鍵となります。
航続距離と積載量の最適化
現在の水素燃料トラックの航続距離はディーゼルトラックに比べるとまだ短く、燃料タンクの大型化による積載量の減少も懸念されています。これらの問題を解決するために、高圧水素タンクの開発や、軽量化技術の向上が求められます。
まとめ
水素燃料トラックは、脱炭素社会の実現に向けた重要な技術の一つとして期待されています。現在は実証試験段階ですが、今後の技術革新とインフラ整備により、商業化が加速する可能性があります。
日本国内でも官民一体となった取り組みが進められており、今後の発展が期待されます。環境負荷の低減と持続可能な物流を実現するために、水素燃料トラックの動向を注視していく必要があります。
岩瀬運輸機工は持続可能な物流業界をめざして、これからも将来に向けた脱炭素化に取り組んでまいります。
岩瀬運輸機構について詳しくはこちら↓↓
参考文献
Hyundai Motor’s Delivery of XCIENT Fuel Cell Trucks in Europe
メルセデス・ベンツの水素燃料電池トラックを試験導入
https://esgjournaljapan.com/world-news/34856
「EV・FCVトラック元年」に熱気、米で導入活発化も残る課題
Hyundai、米国でXCIENT Fuel Cellトラックの市販モデル発表
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000069.000095868.html
日野自動車、ジャパントラックショー2024に出展
https://www.hino.co.jp/corp/news/2024/20240507-003687.html
トラックのエコ技術:持続可能な輸送を支える環境対策

はじめに
近年、環境負荷の低減が求められる中で、トラック輸送業界でもさまざまなエコ技術が導入されています。化石燃料の消費を抑えることは、二酸化炭素(CO2)排出の削減や燃料費の節約にもつながり、持続可能な社会の実現に向けた重要な課題です。本記事では、トラックのエコ技術として注目されるCNG(圧縮天然ガス)、水素燃料、ハイブリッド車、電気自動車(EV)の特徴とメリットについて詳しく解説します。
CNGトラック:低排出でクリーンな選択肢
CNGとは?
CNG(圧縮天然ガス)は、主にメタンを主成分とするガスを高圧で圧縮した燃料です。石油由来の軽油やガソリンと比較して、燃焼時のCO2排出量が少なく、環境負荷を軽減できます。
CNGトラックのメリット
・CO2排出量の削減:ディーゼル車と比較してCO2排出量を20〜25%削減。
・排気ガスのクリーン化:硫黄酸化物(SOx)や粒子状物質(PM)がほとんど発生しない。
・燃料コストの安定性:天然ガスは原油と比べて価格変動が少ない。
課題
・航続距離の制約:燃料タンクの容量によっては、航続距離が短くなる可能性がある。
・充填インフラの不足:CNGスタンドの数が限られており、普及にはインフラ整備が必要。
水素トラック:ゼロエミッションの未来
水素燃料とは?
水素を燃料とする燃料電池車(FCV)は、水素と酸素の化学反応によって電気を発生させ、モーターを駆動する仕組みです。その結果、走行中のCO2排出はゼロであり、環境負荷が極めて低いのが特徴です。
水素トラックのメリット
・CO2排出ゼロ:排出されるのは水のみ。
・充填時間が短い:電気トラックと比較して充填時間が5〜10分程度と短時間。
・長距離輸送に適する:一回の充填で500km以上の走行が可能。
課題
・水素ステーションの整備:水素を充填できるステーションが少なく、インフラ整備が急務。
・車両価格が高い:技術の発展と量産化が進むことで、コスト低減が期待される。
ハイブリッドトラック:燃費効率の向上
ハイブリッド技術とは?
ハイブリッドトラックは、エンジンと電気モーターを組み合わせたシステムを採用し、燃費の向上と排出ガスの削減を実現します。
ハイブリッドトラックのメリット
・燃費効率の向上:エネルギー回生システムにより、ブレーキ時のエネルギーを再利用。
・排出ガスの削減:ディーゼルのみのトラックに比べ、CO2やNOxの排出量が低減。
・都市部での低騒音化:低速走行時に電気モーターのみで走行できるため、騒音を抑えられる。
CNGハイブリッドトラック
近年、ディーゼルと電気モーターを組み合わせたハイブリッドだけでなく、CNGと電気モーターを組み合わせたCNGハイブリッドトラックも開発されています。
・環境負荷のさらなる低減:CNG自体がクリーンな燃料であり、電動モーターと組み合わせることでさらなるCO2削減が可能。
・燃料コストの削減:CNGはディーゼルよりも価格が安定しており、ハイブリッドシステムの併用で燃費の向上が期待できる。
・都市部の配送に適する:低排出で騒音も少なく、都市部の環境規制にも対応しやすい。
今後の技術動向
・固体電池の開発
リチウムイオン電池の次世代技術として、固体電池が注目されています。従来のリチウムイオン電池よりも高いエネルギー密度を持ち、安全性が向上することが期待されています。固体電池を搭載することで、EVトラックの航続距離を延ばし、充電時間の大幅な短縮が可能になります。
・バイオ燃料の活用
再生可能エネルギーの一環として、バイオ燃料の活用も進んでいます。植物由来のバイオディーゼルや合成燃料(e-fuel)は、既存のディーゼルエンジンとも互換性があり、導入が比較的容易です。特に、カーボンニュートラルな燃料として注目されており、輸送業界の脱炭素化に貢献すると考えられます。
・自動運転技術の進展
AIを活用した自動運転技術も進化しています。自動運転トラックは、燃費の最適化や運行の効率化を実現し、ドライバー不足の解決にも寄与すると期待されています。現在、一部ではレベル4(完全自動運転)を目指した実証実験が進められています。
・水素のさらなる普及
水素トラックの普及には、製造コストの低下とインフラ整備が鍵となります。再生可能エネルギーを利用したグリーン水素の生産技術が発展すれば、よりクリーンな水素供給が可能になります。各国で政府支援を受けた水素ステーションの拡充も進んでおり、今後の普及が期待されています。
まとめ
トラックのエコ化は、CO2削減だけでなく、燃料コストの削減や都市環境の改善にも大きく貢献します。今後の技術進展を注視しながら、持続可能な輸送システムを構築していくことが求められます。岩瀬運輸機工としても、エコ技術の動向を注視し、持続可能な輸送に貢献していきます。
※参考URL
https://www.ntsel.go.jp/Portals/0/resources/forum/16files/16-03k.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/green_innovation/industrial_restructuring/pdf/025_04_00.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.env.go.jp/content/900469596.pdf
張堂顧問による勉強会

グループ会社であるイワセトランスポーテーションにて張堂顧問による勉強会を実施いたしました。
2024年問題や働き方改革等について大変ためになる講話をしていただきました。